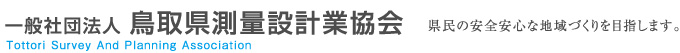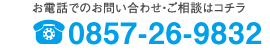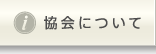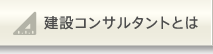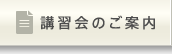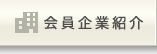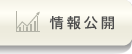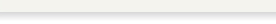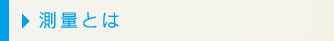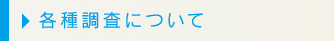「設計」と聞くと、住宅など建築物の設計を思い浮かべる方が多いでしょう。
建築設計では、安全性や機能性などを考慮して建築物の構造や仕様を決め、設計図書(設計図や仕様書)を作成します。これらの設計図書に基づいて建築工事が行われ、建築物ができます。
道路や河川、上下水道などの土木構造物においても、建築設計と同じように、工事の前には安全性や機能性など様々な条件に基づいて構造や仕様を決める土木設計が行われています。
生活や経済の基盤となるインフラ整備を支えるのが土木であり、土木事業の流れの上流に位置するのが土木設計になります。
建築設計では、安全性や機能性などを考慮して建築物の構造や仕様を決め、設計図書(設計図や仕様書)を作成します。これらの設計図書に基づいて建築工事が行われ、建築物ができます。
道路や河川、上下水道などの土木構造物においても、建築設計と同じように、工事の前には安全性や機能性など様々な条件に基づいて構造や仕様を決める土木設計が行われています。
生活や経済の基盤となるインフラ整備を支えるのが土木であり、土木事業の流れの上流に位置するのが土木設計になります。
①初回協議
業務を始めるにあたって、発注者と業務の目的、条件、留意点等について協議します。
②業務計画書作成
業務の実施方針・方法、組織、工程などについて具体的な計画を立て、業務計画書を作成して、発注者に提出します。
③現地踏査
実際に現地に行き、計画地周辺の地形や土地利用状況、交通、構造物、用排水施設、環境など設計計画に必要な現地の概況を把握して記録します。
④基本条件の設定
設計の骨子となる重要な事項を整理し、基本条件として設定します。
⑤設計計画
基本条件に基づき、測量成果(平面・縦横断図など)を使用して詳細な設計を行います。
⑥構造計算
構造物の安全性を数値化して計算します。
⑦設計協議
設計計画案について、発注者と協議して詳細を決定します。
⑧図面作成
計画に基づき、平面図、縦断図、横断図、構造図などの設計図を作成します。
⑨数量計算
設計図に基づき、積算を行うための工事数量(工種や工種ごとの施工量、材料の使用量など)を算定します。
⑩報告書作成
業務の流れや設計成果、留意点などについて取りまとめます。
⑪納品
発注者に設計図や数量計算書、報告書などの成果を確認してもらい、納品します。
⑫完成検査
発注者の検査官による検査を受けます。検査では、成果品が業務目的や契約項目・数量に適合しているかを確認されます。技術的な質問に対し、回答を求められることもあります。
土木は経験則、経験工学と言われますが、一方では資格も重要視される仕事です。
土木設計業務では、業務の管理技術者や照査技術者などに有資格者を配置する必要があります。このため、技術者は仕事をしながら資格取得にも取り組んでいます。
土木設計業務では、業務の管理技術者や照査技術者などに有資格者を配置する必要があります。このため、技術者は仕事をしながら資格取得にも取り組んでいます。
主な資格
●技術士 ●シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) ●土木施工管理技士
●建築士 ●コンクリート診断士 など
●技術士 ●シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) ●土木施工管理技士
●建築士 ●コンクリート診断士 など
土木設計は、土木業界の中でも比較的若者や女性が活躍しやすい職場です。オフィスワークが中心で、図面や資料の作成は全てコンピュータを使用します。
資格取得によるキャリアアップもできますし、CADなどのスキルも身につきますので、結婚・出産後も復帰しやすい仕事です。
資格取得によるキャリアアップもできますし、CADなどのスキルも身につきますので、結婚・出産後も復帰しやすい仕事です。